引用元:東京新聞
1966年に発生した「袴田事件」は、日本の刑事司法史上もっとも有名な冤罪事件のひとつとされています。2024年9月、静岡地裁が袴田巖さんに対して再審無罪判決を言い渡したことは歴史的な出来事でした。検察は控訴を検討しましたが、同年10月8日、畝本直美検事総長が「控訴断念」を表明。その際に公表した談話は、日本社会に大きな反響を与えました。
この記事では、畝本総長の談話全文(要旨)と、その評価・背景を整理し、再審制度や刑事司法への影響について考察します。
畝本直美検事総長 談話の全文(要旨)
2024年10月8日、最高検が発表した畝本総長の談話(要旨)は以下の通りです。
「本判決には多くの問題が含まれており、到底承服できない内容であると認識している。本来なら控訴して上級審の判断を仰ぐべき事件だと考える。
しかし、袴田巖氏が長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、これ以上その状況が継続することは相当でないと判断した。そのため控訴を断念した。
結果として相当な長期間、法的地位が不安定な状況に置かれた点について、刑事司法の一翼を担う検察として申し訳なく思う。」
談話の評価と社会的背景

1. 判決内容への強い不満
談話では「到底承服できない」「多くの問題が含まれている」と表明し、再審無罪判決の妥当性を強く疑問視しました。判決が確定する一方で、検察としては「無罪を完全に認めていない」姿勢をにじませたのです。
2. 控訴断念の理由
- 袴田さんが半世紀以上、死刑囚として不安定な地位に置かれ続けた事実
- 高齢(当時88歳)であり、さらなる裁判継続は人権上問題があるとの判断
この配慮が「控訴断念」という決断に直結しました。
3. 社会的な意義
- 判決確定により、袴田さんは58年ぶりに「死刑囚」という立場から解放
- 異例の「検察による謝罪表明」が盛り込まれ、刑事司法の説明責任が問われる契機に
名誉毀損訴訟への発展
談話には「判決を受け入れていない」という表現が含まれていたため、袴田さん側は2025年9月、国を相手取り名誉毀損訴訟を提起しました。
最高検公式サイトへの謝罪広告掲載を求めており、談話の表現をめぐる新たな司法判断が注目されています。
畝本直美検事総長の立場と異例性

畝本直美氏は2023年に就任した「日本初の女性検事総長」です。
その発言は検察組織全体の姿勢を象徴するものであり、今回の談話は単なる手続的説明を超え、
- 判決への強い不満
- 被告人の人権への配慮
- 検察としての謝罪
を同時に盛り込んだ極めて異例のメッセージとなりました。
今後への影響
まとめ
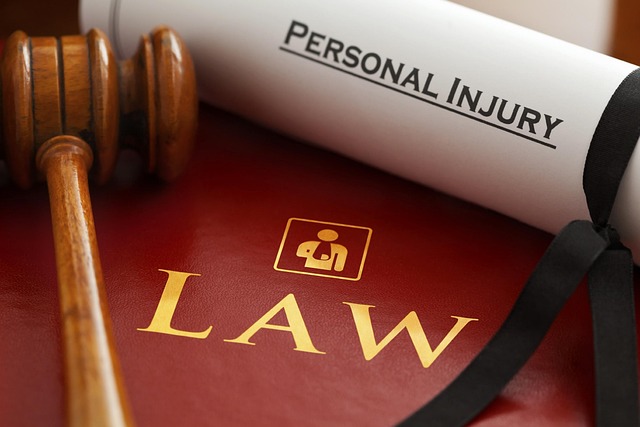
畝本直美検事総長の「控訴断念」談話は、
- 判決を受け入れない姿勢
- 被告人への配慮
- 検察としての謝意
という矛盾を抱えた複雑な内容でした。
それは日本の刑事司法が直面する「冤罪問題」「説明責任」「人権尊重」の難題を象徴する出来事ともいえます。
今後の再審制度や司法改革において、この談話は長く議論され続けるでしょう。
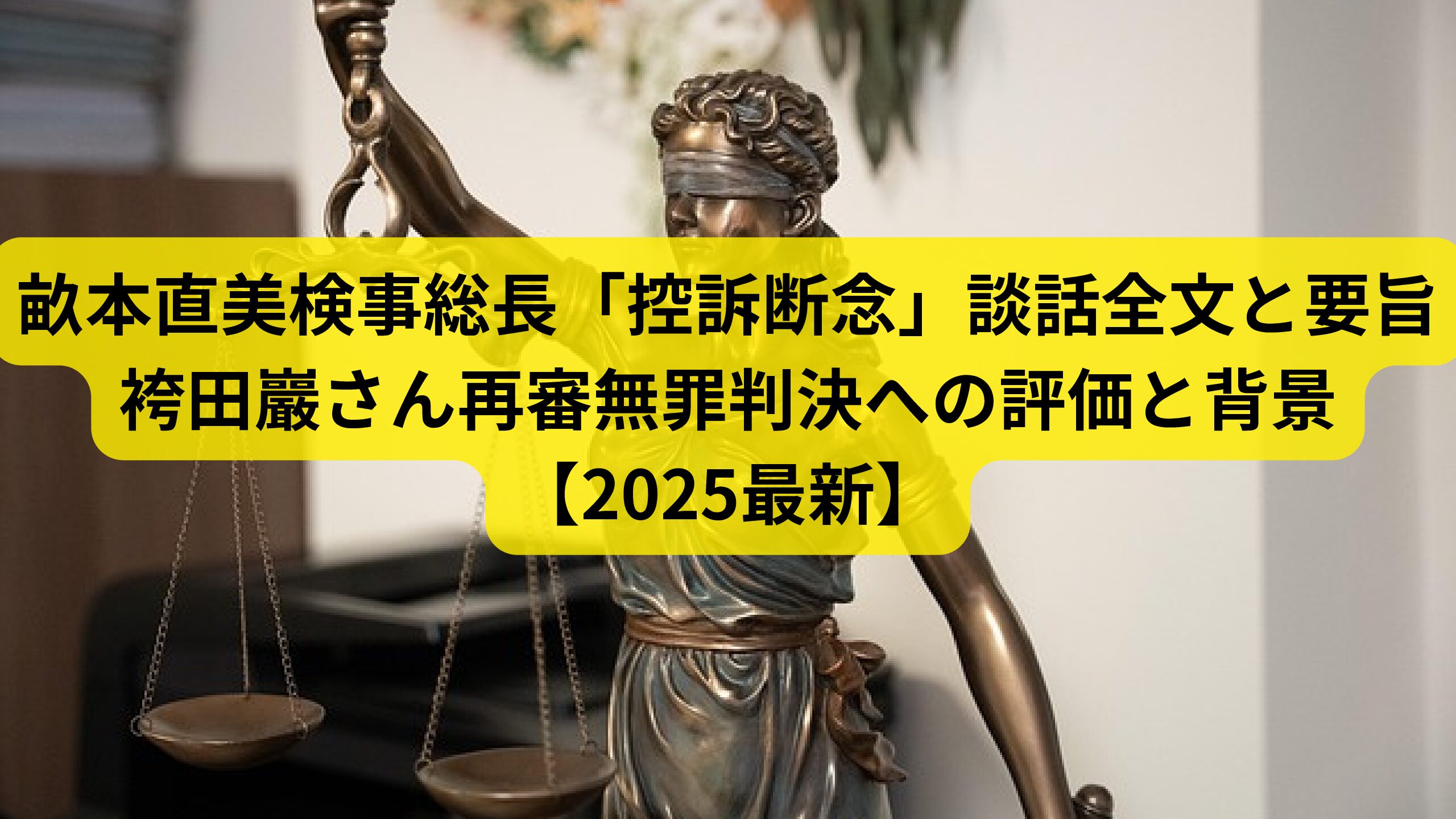


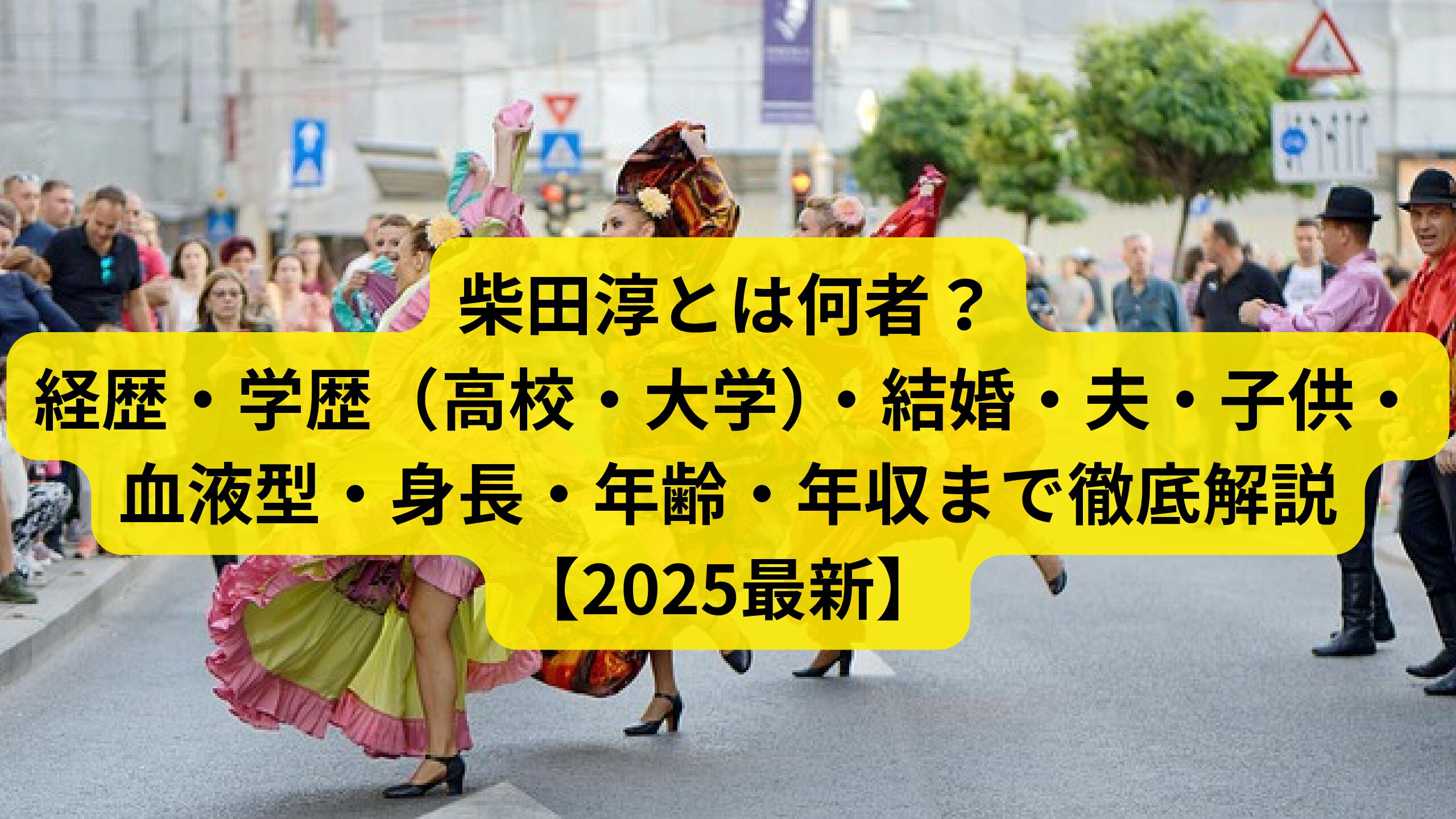
コメント