引用元:まいどなニュース
2025年現在、全国のスーパーやコンビニで進むセルフレジ化の波が、思わぬ形で高齢者の生活に影を落としています。
便利で効率的な仕組みとして注目されてきた一方で、「行きつけの店に行けなくなった」高齢者が急増しているのです。
人手不足やキャッシュレス化の加速により、店舗側の合理化は進む一方。
しかし、現場では「機械が怖い」「スマホを持っていない」「間違えたら迷惑をかける」といった声が広がり、高齢者が買い物そのものを諦める現象が社会問題化しています。
本記事では、セルフレジ普及がもたらす高齢者の“行きつけ喪失”の実態、背景、そして今求められる支援策を専門的に解説します。
セルフレジ化の現状と背景
■ 導入率の急上昇とその理由
経済産業省の調査によると、2025年時点で全国の小売店舗の約65%が何らかの形でセルフレジを導入。
背景には、
これにより、有人レジが縮小し、セルフ操作を前提とした買い物体験が「新たな標準」となりつつあります。
しかしその「標準化」が、デジタル操作に不慣れな高齢層を取り残す結果を生んでいます。
高齢者が「行きつけ」を失う理由

■ ① スマホやセルフレジ操作への戸惑い
多くの高齢者はスマートフォンを持っていない、または基本操作に不安を感じている層が依然として多いのが現実です。
そのため、タッチパネルやQRコード決済が前提のレジでは、「操作ミスをしたらどうしよう」「後ろの人に迷惑をかけるかも」と感じ、心理的プレッシャーが強まります。
結果として、「あの店はもう行けない」と感じ、行きつけを諦めるケースが増えています。
■ ② 対面コミュニケーションの喪失
かつては、レジの店員とのちょっとした会話が“日常の癒し”や“社会的つながり”になっていました。
セルフ化が進むことで、「声をかけてもらえる場所」が減少し、孤立感を深める高齢者も少なくありません。
行きつけの店が「ただ買うだけの場所」になってしまうことで、精神的な居場所の喪失にもつながっています。
■ ③ 店舗のサービス設計が高齢者に不向き
多くの店舗では、導線・表示・操作ガイドが若年層前提のデザインとなっており、
視力や反応速度が低下した高齢者には非常に使いづらい構造です。
また、支払い方法の主流がキャッシュレス化する中で、現金利用者が排除される流れも懸念されています。
これが結果的に、「行きつけだった店に行けなくなった」という現象を加速させています。
行きつけを失うことによる社会的影響
高齢者にとって「行きつけの店」とは、単なる買い物の場ではなく、
セルフレジ化でこの関係が断たれることで、
孤立・うつ・健康悪化といった二次的影響をもたらすことが専門家からも指摘されています。
つまり、これは単なる「買い物の不便さ」ではなく、地域社会全体のつながりが弱まる問題なのです。
高齢者支援と店舗の取り組み事例

■ ① サポートスタッフの常駐化
一部店舗では、**「セルフレジサポート係」**を設置し、高齢者が困った際にすぐ手助けできる体制を整えています。
これにより、「一人でも安心して買い物ができる」という声が増えています。
■ ② わかりやすいUI・案内表示
- 大きな文字
- 音声ガイド
- 高齢者向けチュートリアル動画の導入
など、”視覚・聴覚に優しい設計”を採用する店舗も増えています。
■ ③ 対面サービスとの併用
完全セルフ化ではなく、有人レジを1〜2台残すハイブリッド運用を続ける企業も。
「便利さ」と「安心感」の両立を図る取り組みとして注目されています。
■ ④ 事前ヒアリングと地域連携
導入前に地域の高齢者から意見を聞くワークショップを行う店舗も登場。
この「利用者視点の設計」が、トラブル減少と満足度向上につながっています。
今後の課題と展望

セルフレジは今後もさらに進化し、AIや顔認証などが組み込まれる見通しです。
しかし、それと同時に求められるのは、**「誰もが安心して利用できる仕組み」**の構築です。
行政・企業・地域社会が連携し、
まとめ
セルフレジの普及は、効率化・省人化という時代の流れの象徴です。
しかしその裏で、「行きつけを失う高齢者」が増加し、買い物が心理的にも社会的にも難しくなる現実が広がっています。
“便利さ”の裏にある“人とのつながり”の喪失。
高齢者に優しい社会を実現するためには、「デジタル」と「人間味」の共存が不可欠です。
セルフレジ時代に求められているのは、単なる技術の進歩ではなく、人に寄り添うサービスの再設計なのです。
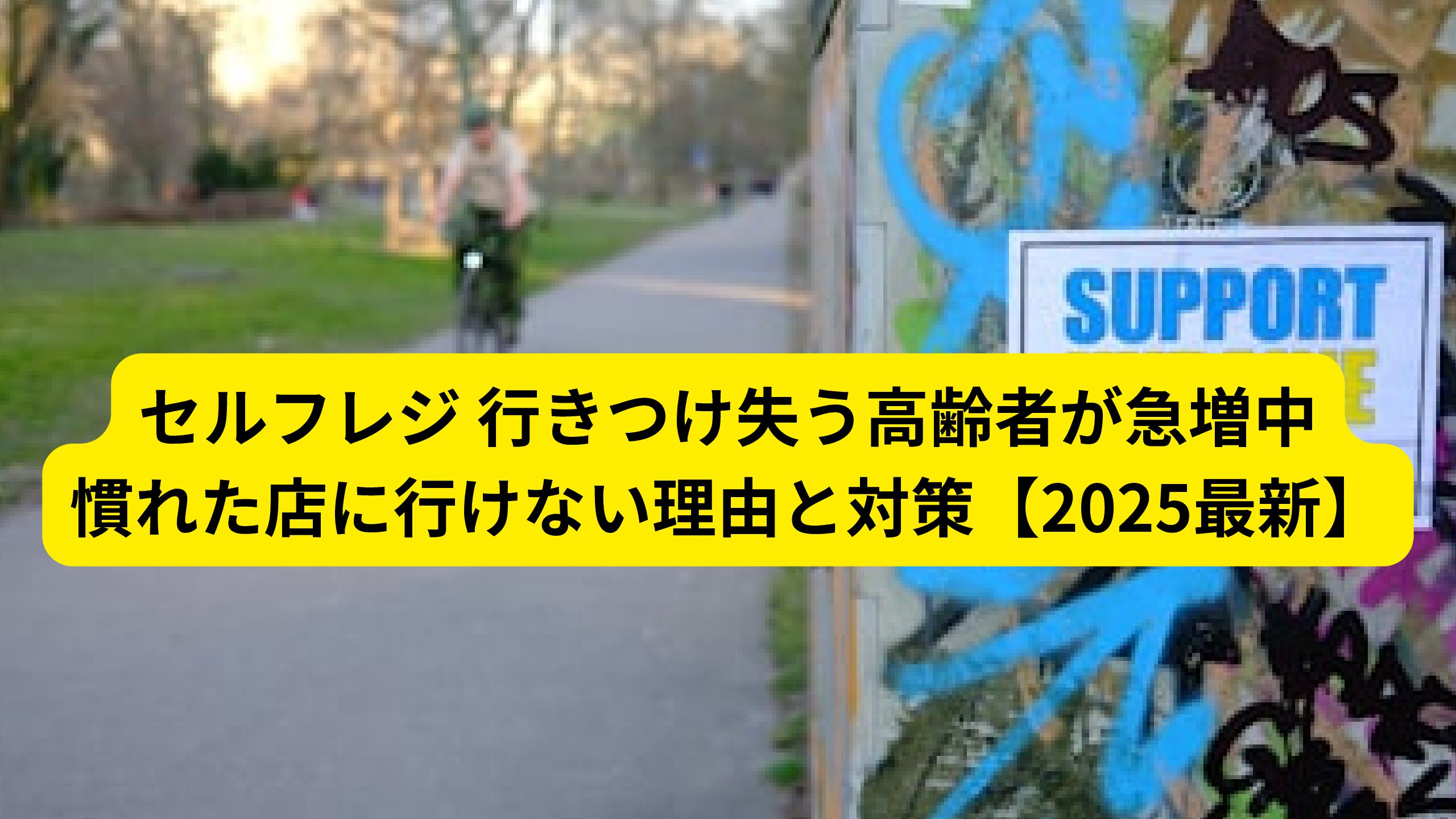

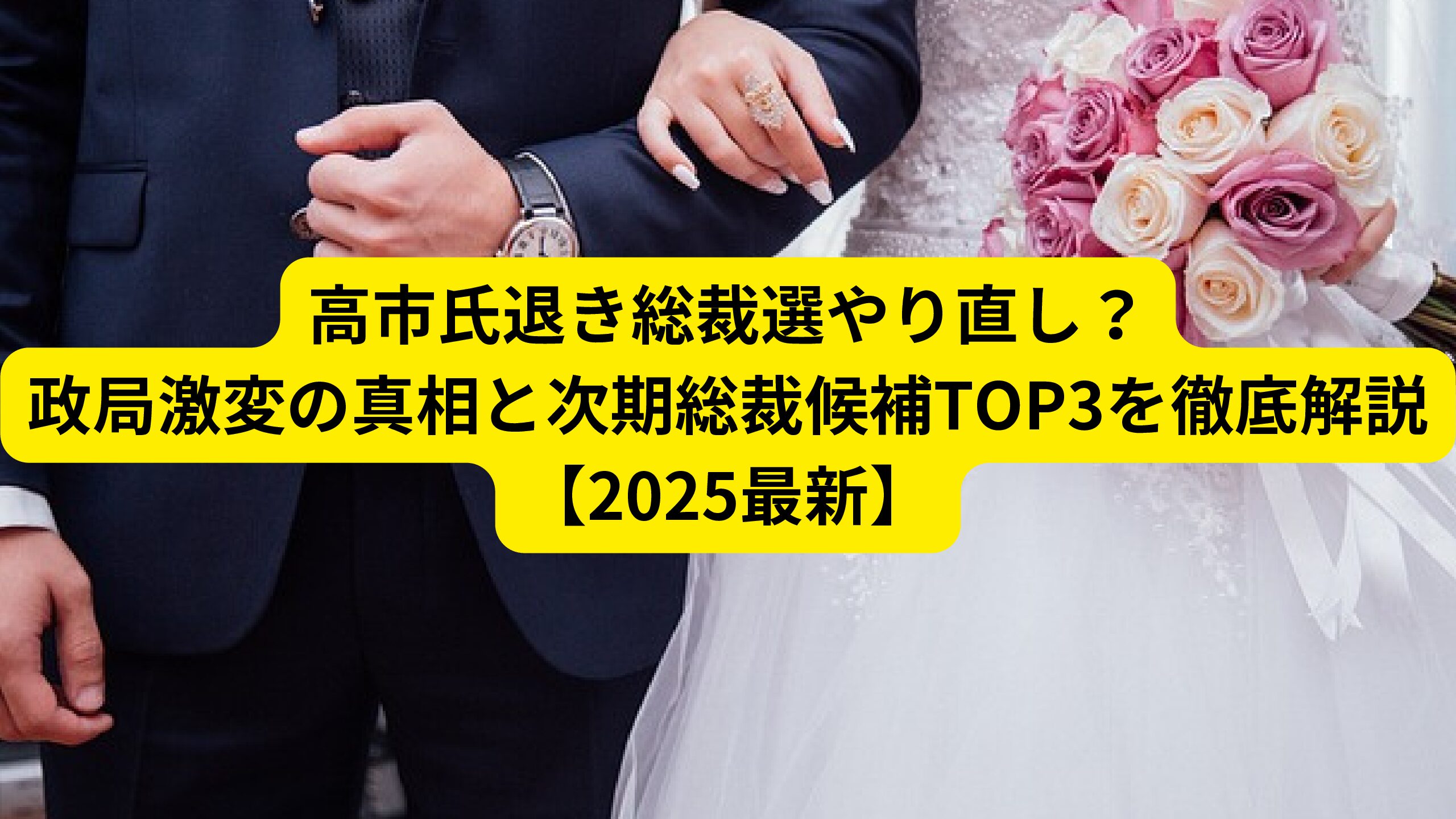
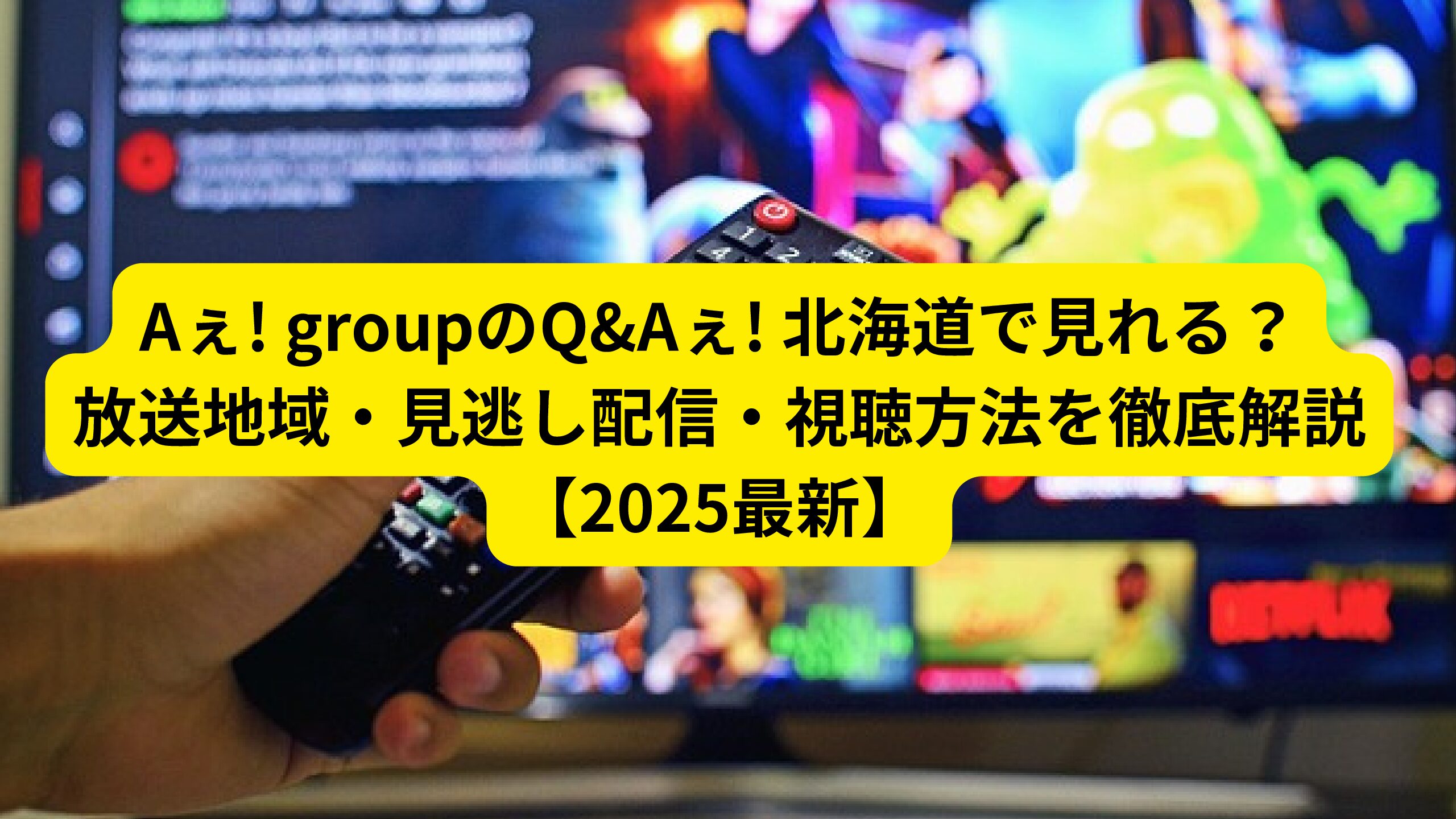
コメント