引用元:Steinberg
「なんでこんなに面白くてクセになるの?」
そう思わせる楽曲を次々と世に送り出す岡崎体育。彼の音楽は、ただ奇抜なだけではありません。
緻密な構成、笑えるのに心に刺さる歌詞、そして“ライブでウケる”という究極の実用主義。
この記事では、岡崎体育がどのように曲を作っているのか、彼自身が語ったプロセスを5つのステップに分けて解剖します!
① テーマ設定からすべてが始まる

岡崎体育の曲作りは、明確な「コンセプト」設定から始まります。
たとえば、
「木村カエラ風のウェディングソングだけど、新郎の家庭環境が複雑すぎる曲」
といったように、一文で内容を言い切れるアイデアから着手。
奇抜な発想なのに、リアルな感情が潜んでいるのがポイントです。
② アイデアを無心にDAW(Cubase)へ投入!

次に行うのは、思いつく限りのフレーズ・リズム・コードを“とにかく足していく”作業。
DAWソフト「Cubase」で素材を重ねに重ね、「余白」よりも「混沌」を一度作り出します。
これは、“自由な遊び”を許すフェーズで、頭で考えず感覚で走ることが重要。
③ 歌詞&構成:面白さと実験精神が全開!

歌詞は、日常観察やパロディ、社会風刺などから生まれたユーモアが軸。
構成も「Aメロ→Bメロ→サビ」という王道にこだわらず、
- サビから始まる
- 2番が異様に短い
- ブリッジで語り始める
など、型破りな展開も多用されます。
とはいえ、初心者には「3分10秒の定番構成」を推奨しており、彼の中にしっかりと“セオリー”もあるのです。
④ 引き算で“核”を研ぎ澄ます
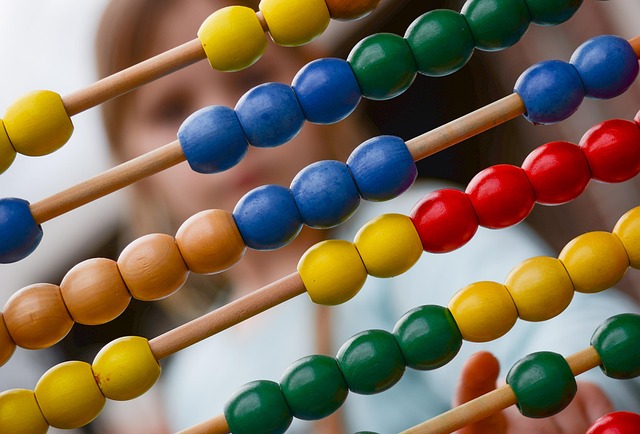
素材を出し尽くしたあとは、余計なものをそぎ落とす“引き算”フェーズへ。
楽曲の中で「何を伝えたいのか?」を明確にし、それ以外は潔くカット。
特にサビ前やエンディングは「どれだけ残すか」ではなく「何を消すか」で勝負。
音の間(ま)や、展開のギャップが際立つのはこの作業によるものです。
⑤ ライブとSNSで“検証”して完成へ

最大の特徴がこれ。
完成版をレーベルやディレクターに見せる前に、ライブで客の反応を見て判断します。
「笑った?ざわついた?それなら採用」
「反応薄かった?はい、ボツで!」
というように、“ウケるかどうか”が最終判断基準。
エンタメを極めるプロとして、最後は自分の感性ではなく“現場の声”を信じる姿勢が光ります。
🎵 岡崎体育の曲作り5ステップまとめ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① テーマ設定 | 奇抜かつ共感性あるコンセプトを言語化 |
| ② 素材出し | Cubaseでとにかくアイデアを重ねる |
| ③ 歌詞&構成 | 社会風刺と意外性ある構成で遊ぶ |
| ④ 引き算 | 最も伝えたい要素だけを残す |
| ⑤ 検証・改良 | ライブやSNSで反応を見て最終調整 |
まとめ
岡崎体育の楽曲は「奇抜さ」ではなく、「戦略的な笑い」と「実験精神」でできています。
自宅で完結する制作環境、母親や観客の声を取り入れる柔軟さ――。
そのすべてが、“一度聴いたら忘れられない曲”を生み出す源泉です。
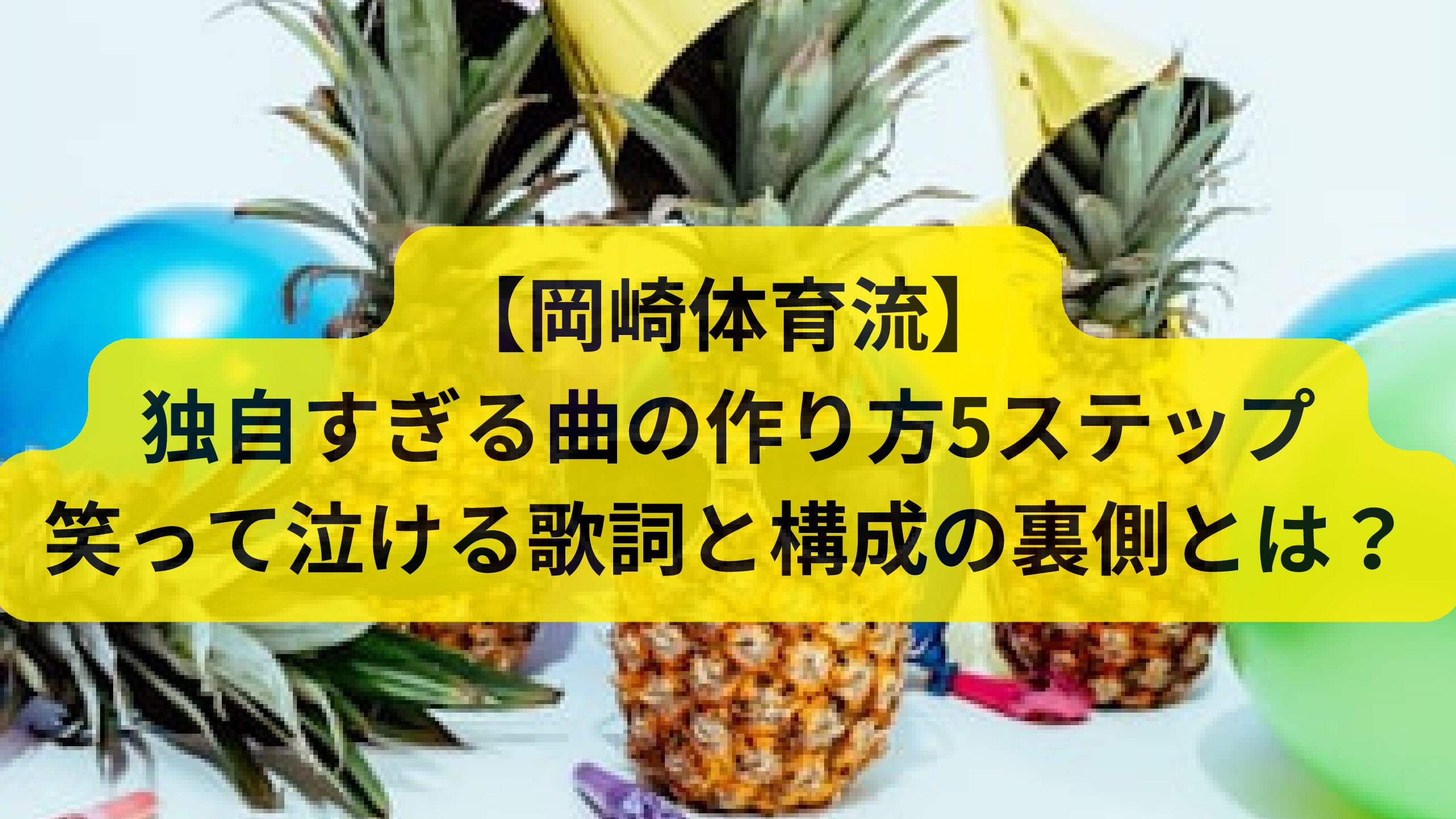

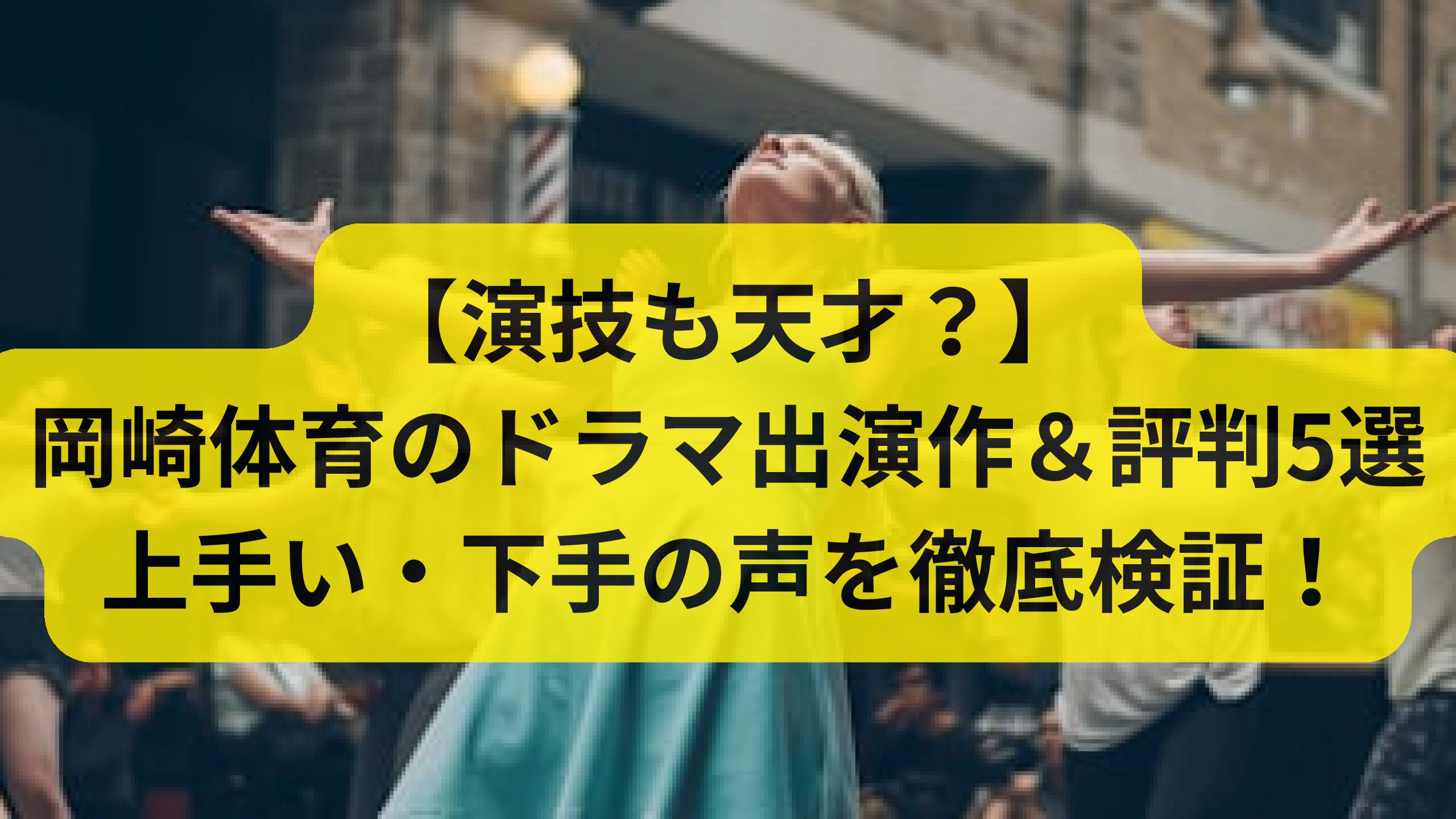
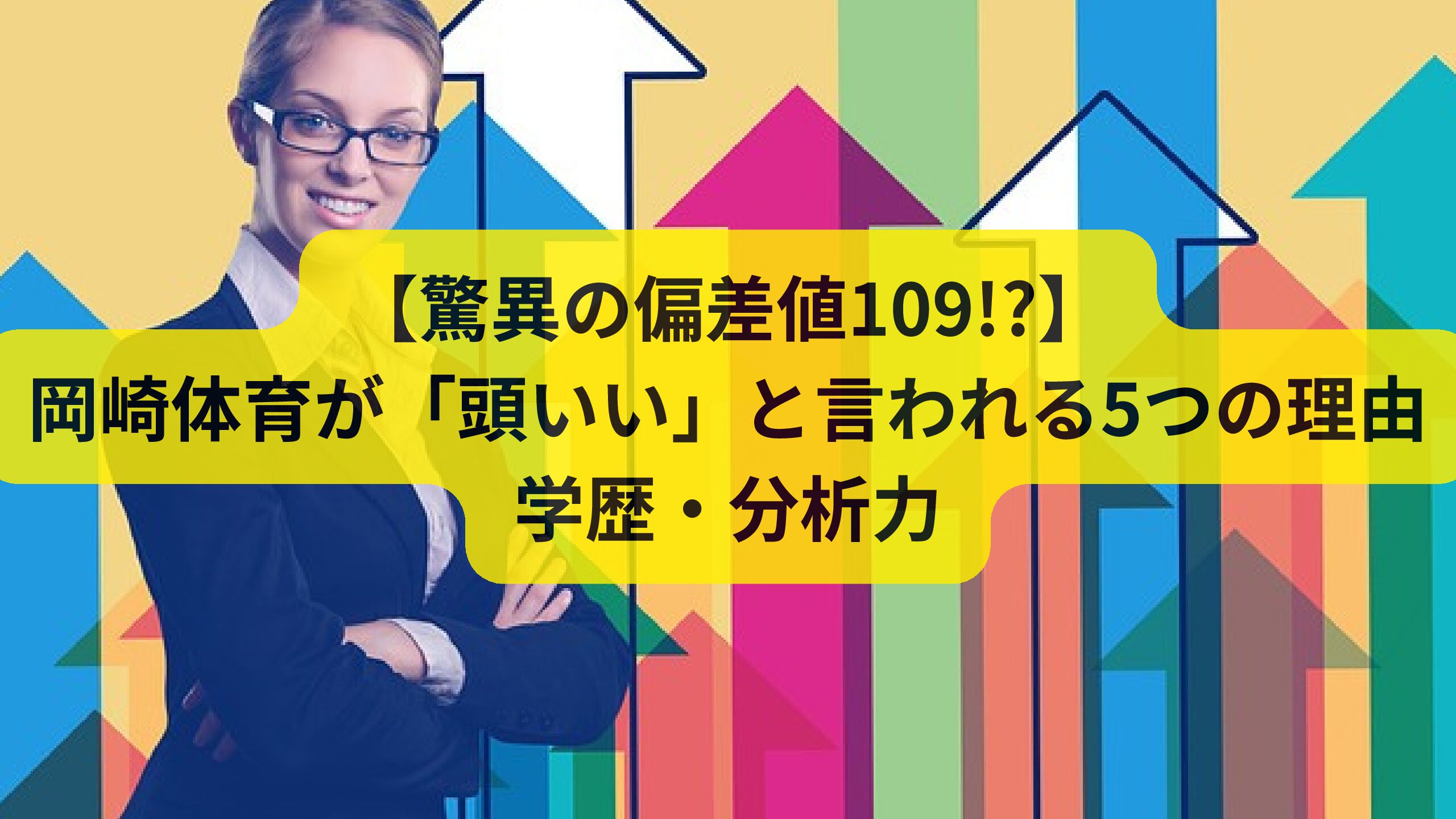
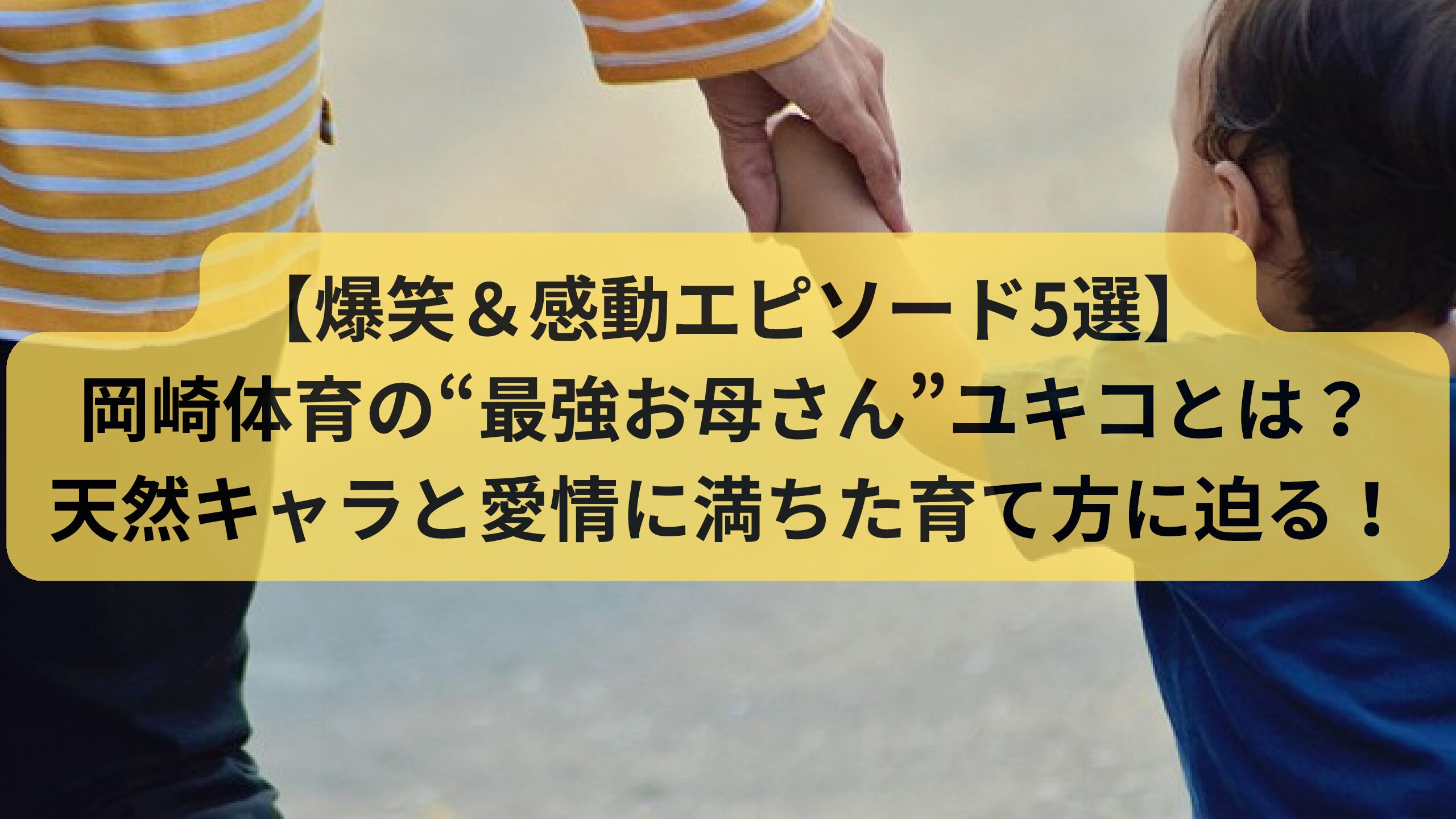
コメント