引用元:Yahoo!ニュース – Yahoo! JAPAN
近年、サッカーW杯は複数国共催がスタンダードとなり、2026年大会(アメリカ・カナダ・メキシコ)、2030年大会(スペイン・ポルトガル・モロッコほか6カ国)と、グローバルな協調開催が続いています。
そして注目されるのが、2046年W杯の「アジア広域共催構想」です。
■ 日本・韓国・中国など東アジア各国
■ インドネシアやタイ、ベトナムなどASEAN諸国による「多国間連合」
■ “再びの日韓共催”を視野に入れたクラシックな共催案
アジア全体を巻き込んだ招致競争が、水面下で始まっています。
FIFAの「大陸持ち回り」制と開催予測

FIFAは公式制度ではないものの、W杯の開催地を原則大陸ごとにローテーションしています。
2034年にアジア(中東)開催が決定しているため、2046年は“東アジアまたは東南アジア”が本命とみられています。
日本・韓国による“2002年再現”案

日本サッカー協会(JFA)は2046年W杯招致を本命に位置づけ、韓国や中国など東アジア各国と連携を模索中。
JFAと韓国協会は、実際に複数の会合や連携協議を重ねており、「運営実績」「インフラ充実」「治安・交通網」といった2002年大会で評価された強みを再アピールしています。
メリット
課題
ASEAN(東南アジア)中心の多国共催案

ASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国による「新興市場型共催」も有力視されています。
インドネシア・タイ・ベトナム・マレーシア・シンガポールなど、6億人規模の巨大市場を背景に観光資源、若年人口を武器としたチャレンジです。
強み
課題
広域アジア連携型――「夢の大陸共催」シナリオ

日本・韓国・中国・ASEAN諸国が連携し、東アジア・東南アジアを横断するアジアワイドW杯が現実味を帯びる最大の理由は、
- 出場国48→64カ国規模への拡大(現実的に単独開催が困難)
- 交通・宿泊・商業インフラの分散化で経済波及効果を最大化
- スポーツを通じたエリア統合・外交促進
というFIFAのトレンドや理念と完全に合致しているためです。
その他のライバル開催案
とはいえ、現状では「アジア広域連携案」が、FIFAの「多様化・負担分散・成長市場志向」と最も整合性が高い流れといえます。
FIFAが複数国共催を推進する3つの理由

①インフラ負担の分散
出場国・試合数・観客が増えた現W杯では、単独開催はもはや大きなリスク。複数国が連携しインフラを有効活用できる形が主流に。
②グローバルなサッカー普及とマーケット戦略
新興エリアや多様な文化圏のファン層開拓が不可欠。複数国での開催はサッカーの“世界標準化”に合致。
③地域間の協力推進
W杯を“グローバル・パートナーシップの象徴”に据え、各国の連携と調和を演出。
まとめ|2046年W杯は“アジア広域共催”が時代の要請
「世界一多様なアジアW杯」が誕生する日は、そう遠くないかもしれません。アジア発・次世代ワールドカップのゆくえに、今後も大注目です
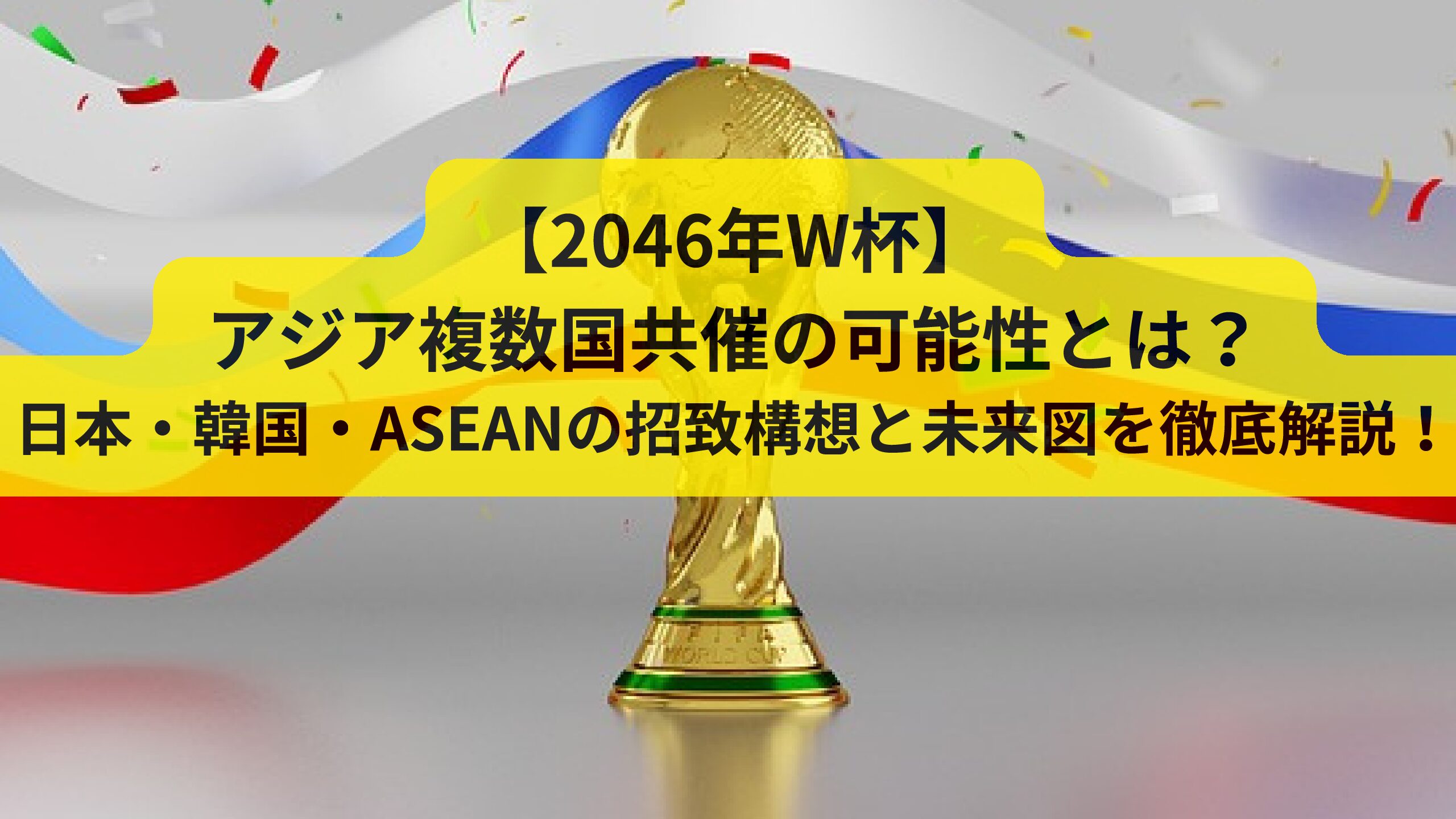

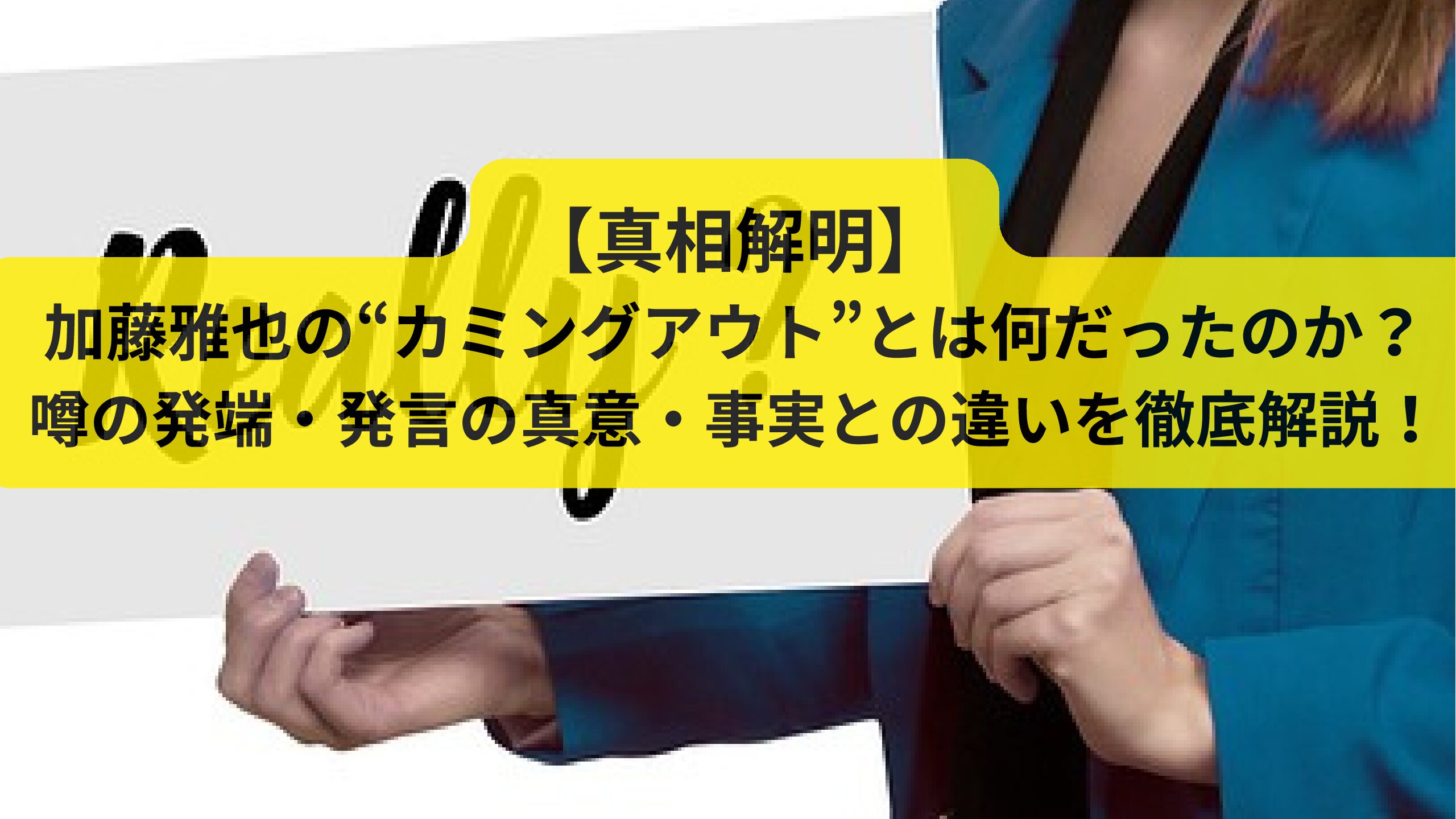
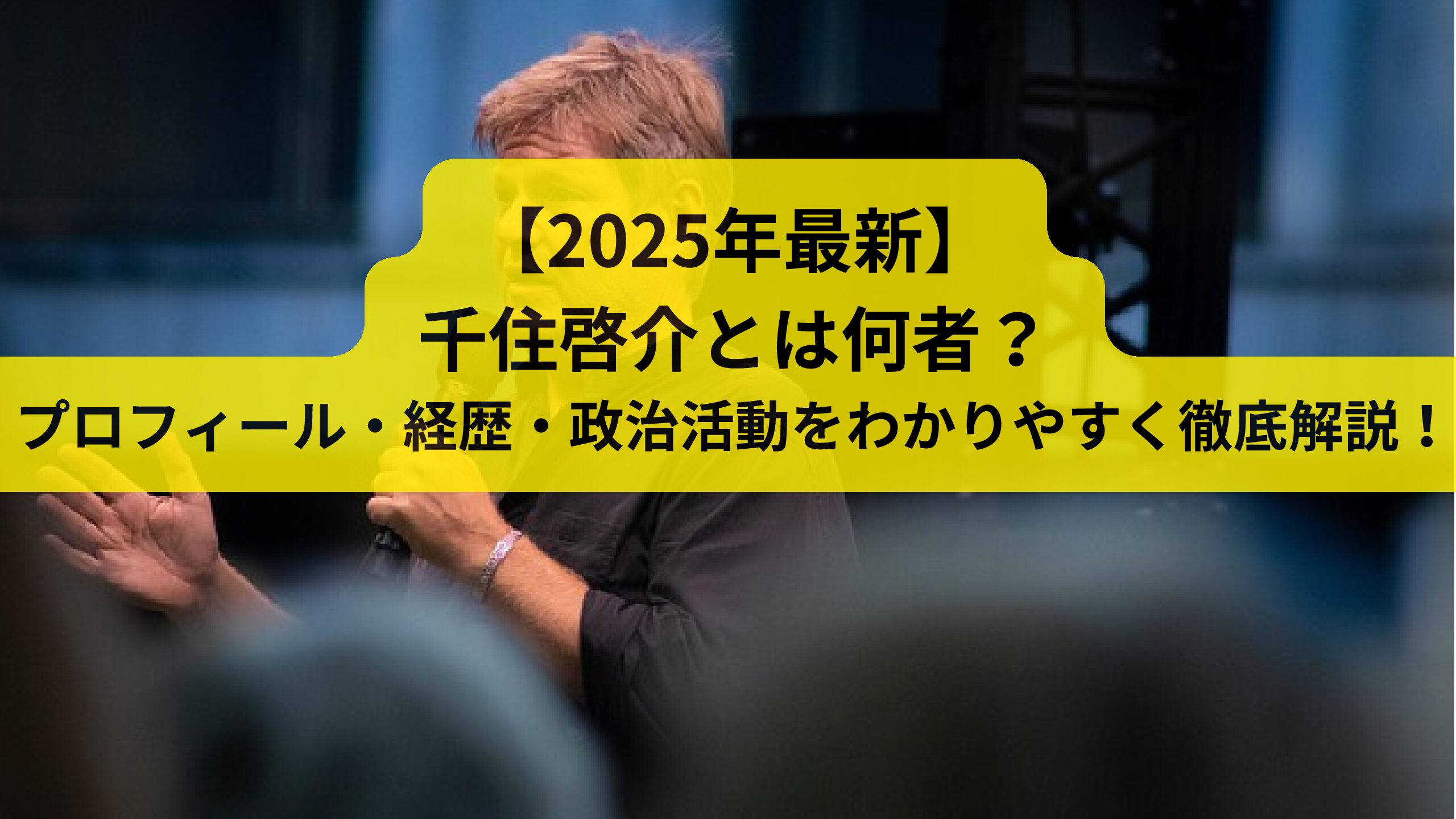
コメント